嵐の夜にとどろく雷鳴、落ちる稲妻。人々にとって恐ろしい自然現象である雷がなぜ起こるのかを解説
子供にとって恐ろしい自然現象である雷。大人になっても怖いものですよね。
稀に人に落雷が当たって大けがをしたり、命を落とすなんてことも。
古来からこの自然現象は様々な国で神格化され、日本の民間伝承でも「風」という自然現象と共に「風神・雷神」として崇められてきました。
親しみを込めて雷様などと呼び、大きな音を出すことから太鼓を背に抱え、雲に住んでいる鬼のような見た目で擬人化されるなど、単に恐ろしい存在だけでなく身近な存在でもあると言えます。
また、稲妻はかっこいいモチーフとして様々な表現に取り入れられています。
ただ、なぜ上空に雷のような電気が生じ、大きな音を出して落ちてくるのか?その仕組みを理解していきましょう。

結論:雲粒の摩擦で静電気が生じ、放出する際に空気を急激に熱することで音が発生する
雲を構成する細かな水や氷の粒が衝突により電気が蓄えられる
雲は空気中の水蒸気が冷やされてできた細かい氷や水の粒で構成されています。
地上へ落ちていくこれらの粒と、上空へ上昇する粒などが衝突する際に静電気が発生します。
その電気が雲の中に蓄えられていきますが、蓄えきれなくなると放出されます。
電気はプラスとマイナスの電極の間を移動するので、放出された電気は上空か地上のプラスの電極へ向かって放出されます。
地上のプラス方向へ放出された電気が雷の正体です。
なお、電流はプラスからマイナスへ移動すると言われていますが、電子はマイナスからプラスに移動します。雷は空気中の電子が放出される現象なので、マイナスからプラスへ移動しています。
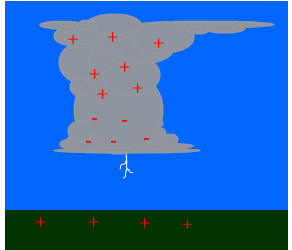
雷は強い光を発生させますが、それを雷光や稲妻などと呼びます。
ちなみに雲が発生する仕組みは以下の記事で紹介しているので合わせてご覧ください。
なぜ雷光はギザギザの形をしているのか?
雷光は独特のギザギザした形をしていますよね。
なぜあのような形になるのでしょうか?
通常、空気は電気を通しません。電気は金属などの物質の中を流れます。
しかし、非常に強い電気である雷は絶縁体である空気をも通っていきます。空気の中を無理やり通るので、取りやすいルートを探しながら移動することによりギザギザの形をした光を放ちます。
例えていうのであれば、混雑した道を歩く際に人を縫って進んでいくと進路が真っすぐではなくギザギザになってしまうのと同じです。

電気なのになぜ音が鳴るのか?
雷と言えば、あのゴロゴロとした音。落雷をするときはズドーンという大きな雷鳴を放ちます。
この音の正体はなぜ発生するのでしょうか?
上で説明したように、雷は空気の中を無理やり通過していきます。
その際に電気が発する約2~3万℃にものぼる高い温度ため空気を急激に温め膨張させます。その際の空気の振動により音を発します。
落雷の際の雷鳴は、急激な空気の温度上昇により衝撃波が発生したことによるものです。地上に落ちた際の衝撃音ではありません。
雷が起きる理由まとめ
- 雲の中の水や氷の粒が衝突した摩擦によって静電気が発生する
- 静電気を蓄えきれなくなった雲から地上へ放電される
- 通常は電気を通さない空気中を無理やり電気が通り発光するのが雷光
- 空気中のなるべく通りやすい経路をたどって電気が移動するので雷光はギザギザの形になる
- 電気の熱で急激に膨張した空気が音を発生させるのが雷鳴である





